葬儀を終えたばかりのご遺族は、心身ともに疲れ果てていることと思います。しかし、葬儀が終わった後も、故人の供養や手続き、挨拶回りなど、やるべきことは少なくありません。この記事では、葬儀後の流れや、喪主として知っておきたいマナー、各種手続きについて、網羅的に解説します。
葬儀後の流れとやるべきこと

葬儀後の流れは、大きく分けて以下の6つに分類されます。それぞれの段階で、何をすべきか見ていきましょう。
1. 火葬・収骨
葬儀の後は、ご遺体を火葬場へ運び、火葬を行います。火葬場には、故人と特に近しいご遺族が向かいます。そこでは、最後のお別れとして読経や焼香が行われます。火葬後は、ご遺骨を骨壷に納める「収骨(お骨上げ)」を行います。地域によっては、ご遺族が箸を使って収骨する風習があります。特に「喉仏」の骨は重要視され、丁寧に扱われます。収骨されたご遺骨は、一般的に喪主が管理します。
2. 精進落とし(食事会)
火葬後には、初七日法要を兼ねて、ご親族や参列者で食事をする「精進落とし」が行われます。これは、故人の供養と、参列してくれた方々への感謝を伝えるための大切な場です。食事をしながら、故人の思い出を語り合うことで、故人を偲び、心を落ち着かせることができます。
3. 各種手続き
葬儀後には、さまざまな手続きが待っています。
- 葬儀費用の支払い:葬儀社への支払いを済ませます。
- 公的手続き:役所への死亡届の提出は、通常7日以内に行います。年金や健康保険の手続きも、期限内に進める必要があります。
- 相続手続き:故人の財産に関する相続手続きを行います。必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
- 各種契約の変更:故人名義の銀行口座、公共料金、クレジットカードなどの名義変更や解約を行います。
これらの手続きは、期限が定められているものも多いため、計画的に進めることが大切です。
4. 挨拶回り
葬儀で大変お世話になった方々へのお礼の挨拶回りも重要です。お手伝いいただいた方、供花をいただいた方、近隣の方々へ、感謝の気持ちを伝えましょう。訪問する際は、地味な服装を心がけ、男性はネクタイを着用するのが一般的です。
5. 法要の準備・実施
四十九日法要、百か日、一周忌など、今後の法要に向けての準備を始めます。また、お墓や仏壇がまだない場合は、この期間に手配を進めます。法要の日程や場所、参列者などを決めて、準備を進めましょう。
6. 遺品整理と相続の準備
故人の遺品整理を始め、相続や名義変更などの準備を計画的に進めます。遺品整理は、故人を偲ぶ大切な時間でもあります。急がず、故人の思い出を大切にしながら進めましょう。
葬儀後の挨拶とメールの送り方
葬儀が終わった後、感謝やねぎらいの気持ちを伝えるための挨拶や連絡は、ご遺族にとっても、弔問に訪れた方々にとっても大切な時間です。
葬儀後の挨拶
挨拶は、故人への供養と参列者への感謝を伝える大切な場面です。
主な挨拶のタイミング
- 出棺前や火葬場での挨拶:見送りに来てくれた方々へ、感謝と別れの言葉を伝えます。
- 火葬後・精進落としの席:喪主から、無事葬儀を終えられた報告とお礼を述べます。
- 後日、参列やお手伝いをしてくださった方への個別挨拶・回礼:電話や訪問、お礼状などで、改めて感謝を伝えます。
挨拶のポイント
- 簡潔に:長く話しすぎず、感謝の気持ちを簡潔に伝えます。
- 忌み言葉を避ける:「重ね重ね」「再び」など、不幸が繰り返されることを連想させる言葉は使いません。
- 感謝を伝える:「おかげさまで」「お力添えを賜り」など、感謝の言葉を中心に構成します。
葬儀後のメール
最近では、遠方で参列できなかった場合など、葬儀後にメールでお悔やみやお礼を伝えることが増えています。
メールを送る際の注意点
- 相手に配慮する:メールは略式のため、目上の方や特に礼儀を重んじる相手には控えた方が無難です。
- 件名を簡潔に:件名に「〇〇です お悔やみ申し上げます」など、内容が一目でわかるようにします。
- 忌み言葉を避ける:死や不幸を連想させる直接的な表現は避け、「ご逝去」「ご永眠」などの言葉を使います。
- 返信は不要と添える:相手が返信に気を使わないよう、「返信は不要です」と一言添えましょう。
メールの文例
【一般的なねぎらいのメール】
件名:〇〇です お悔やみ申し上げます
このたびはご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。 本来であればご弔問に伺わなければなりませんでしたが、葬儀でのお役目お疲れのことと存じますので、略儀ながらメールにて失礼いたします。
どうぞ気を落とさずお身体にお気をつけください。 〇〇さまの安らかなご永眠をお祈りいたします。
なお、メールの返信は不要です。
【友人へのメール】
件名:〇〇よりお悔やみ申し上げます
お父様のご逝去を知り、驚いてメールしました。 本来であれば弔問に伺うべきですが、遠方のため参列できず申し訳ありません。
無理をしているのではないかと心配しています。 あまり力を落とさず、心身にお気をつけください。 本当に大変だったと思います。お手伝いできることがあれば、いつでも声をかけてくださいね。
メールへの返信は不要です。
葬儀後の香典と「お清めの塩」
葬儀後に香典を渡したり、「お清めの塩」を使ったりすることには、それぞれ意味とマナーがあります。
葬儀後の香典
香典は、本来は通夜や葬儀の際に持参するものですが、参列できなかった場合は後日渡しても失礼にはあたりません。
渡す際のマナー
- 事前に確認する:ご遺族に、弔問や香典を渡してよいか事前に確認するのがマナーです。
- 渡し方:後日訪問して直接渡すか、遠方の場合は現金書留で郵送することも可能です。
- 表書き:四十九日までであれば「御霊前」、それ以降は仏教では「御仏前」とします。
- 金額の相場:故人との関係性によって異なります。祖父母で1〜5万円、叔父・叔母で1〜3万円、知人は3千円〜1万円程度が目安です。
お清めの塩
「お清めの塩」は、日本の伝統的な風習で、葬儀で身についた「穢れ(けがれ)」や「邪気」を祓うために使われます。
塩の正しい使い方
- 帰宅時:家に入る前に、玄関の外で塩を使います。
- 塩をかける順番:胸、背中、足元の順に軽く振りかけます。
- 手で払う:振りかけた塩を手で払い、服についた塩を落とします。
- 踏んでから入る:最後に足元の塩を踏んでから家に入ります。
この風習は主に神道の影響が強く、仏教でも地域や宗派によっては使わない場合があります。無理に行う必要はなく、ご自身の気持ちに合わせて対応しましょう。
葬儀後、ご自宅に弔問客が来られた際の対応
葬儀後、ご自宅に弔問客が訪れることがあります。故人を偲び、ご遺族をねぎらう気持ちで来てくださった方々に対し、丁寧に対応することが大切です。
弔問客への対応
- 事前に確認:弔問客には、事前に来訪日時を伝えてもらい、ご遺族の都合を確認します。
- おもてなし:お線香をあげていただき、お茶やお菓子を用意して対応します。
- 挨拶と言葉遣い:玄関でお悔やみの言葉を述べ、家に招き入れます。長居はせず、相手の負担にならないように配慮します。帰り際には「お体を大切に」など、労りの言葉をかけましょう。
まとめ
葬儀が終わった後も、ご遺族には多くの役割があります。しかし、一人で全てを抱え込む必要はありません。葬儀社や専門家、周囲の方々に相談しながら、少しずつ、ご自身のペースで進めていくことが大切です。故人を偲び、感謝を伝えるこの期間が、ご遺族の心の整理につながることを願っています。

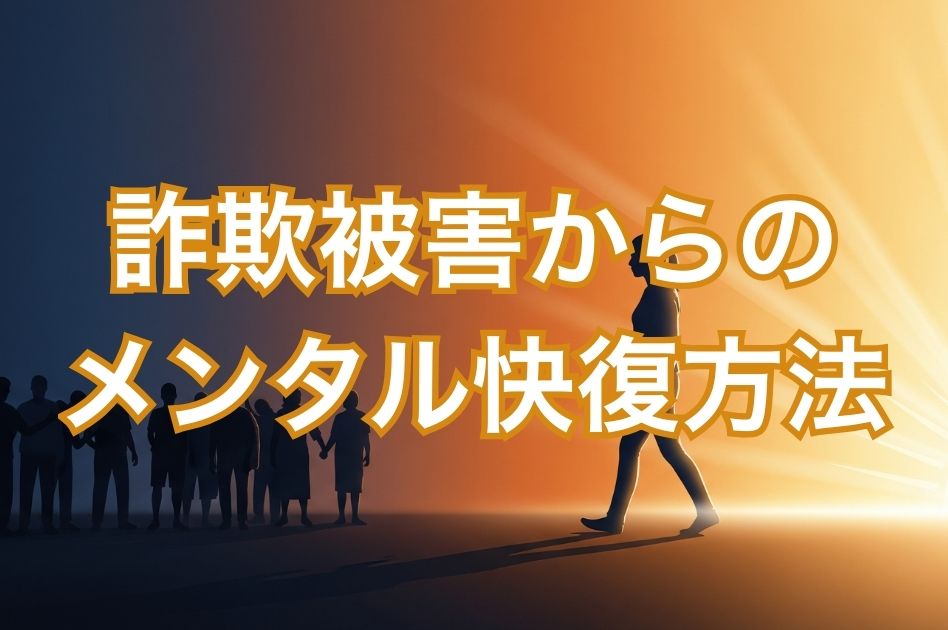
コメント